
「どうしても犬を手放さなければならない状況になったけど、愛犬との別れを考えるだけで胸が痛くて仕方ない…」
愛犬を手放さなければならない状況に直面すると、深い悲しみや罪悪感に襲われることがあります。長年家族として過ごしてきたパートナーとの別れは、想像以上に辛いものです。
- 犬を手放す決断をしても、なぜこんなに苦しい気持ちになるの?
- 避けられない状況でも、少しでも心が楽になる方法はある?
- 犬にとっても飼い主にとってもベストな選択肢は何だろう?
そこで今回は、「犬を手放せない気持ち」に焦点を当て、その心理的な背景から具体的な対処法まで詳しくお伝えしていきます!
犬を手放せない気持ちの心理的背景とは

まず、なぜ私たちは犬を手放すことにこれほど苦しみを感じるのでしょうか。この感情には、深い心理的背景があります。
犬と人間の絆は特別です。科学的研究によれば、犬と触れ合うことでオキシトシンというホルモンが分泌され、強い愛着感情が生まれることが分かっています。このホルモンは母子間でも分泌される「愛情ホルモン」と呼ばれるものです。
また、長年一緒に生活してきた犬は単なるペットではなく、家族の一員としての存在感を持っています。毎日の生活習慣や思い出が積み重なることで、より深い絆が形成されるのです。
そのため、犬を手放す決断は、家族との別れに等しい喪失感をもたらします。この感情は「ペットロス」に似た心理状態を引き起こすこともあるでしょう。
実際、犬を手放した後に抑うつ症状を経験する人は少なくありません。これは「予期的悲嘆」と呼ばれる心理状態で、別れを前にして感じる喪失感や悲しみのことです。
このように、犬を手放せない気持ちは、単なる寂しさではなく、深い愛情と絆に基づく自然な感情反応なのです。
やむを得ず犬を手放す一般的な理由

犬を手放さなければならない状況は、多くの場合避けられない事情から生じています。どのような状況で飼い主が犬との別れを決断するのか、主な理由を見ていきましょう。
引っ越し・住環境の変化
最も多い理由の一つが、引っ越しや住環境の変化です。新しい住居がペット不可である場合や、海外赴任のため一緒に連れていけない状況などが挙げられます。特に賃貸物件では、ペット可の物件を見つけることが難しい場合もあるでしょう。
この状況では、新たな住居を探す際にペット可の物件を優先的に検討することも一つの選択肢です。最近はペット可の物件も増えていますが、条件や家賃が折り合わないケースも少なくありません。
経済的な問題
犬の飼育には、食費、医療費、グルーミング費用など、継続的な経済的負担がかかります。特に大型犬の場合や、犬が高齢になって医療費がかさむ場合には、経済的な理由から飼育継続が困難になることもあります。
実際、犬の飼育にかかる年間費用は、犬種やサイズによって異なりますが、小型犬で約15万円、大型犬では30万円以上になることも珍しくないのです。予期せぬ病気や怪我で突然高額な医療費が必要になることもあります。
家族の事情(アレルギー・病気など)
家族にアレルギーが発症した場合や、家族の病気・怪我により犬の世話ができなくなるケースもあります。特に子どもが生まれてからペットアレルギーが判明するケースは珍しくありません。
このような場合、アレルギー対策や犬の飼育スペースの分離などの工夫を試みても改善しないこともあるのです。家族の健康を優先せざるを得ない状況は、飼い主にとって特に辛い選択となります。
犬自身の問題行動や適応の難しさ
犬の問題行動(咬みぐせ、吠えすぎなど)や、飼育環境への適応困難が理由となるケースもあります。特に集合住宅では、近隣とのトラブルに発展することもあるでしょう。
このような場合、動物行動学の専門家やトレーナーに相談することで問題が解決することもあります。しかし、犬種や個体差、環境要因などによっては、問題解決が難しいケースも存在します。
飼い主の高齢化や健康問題
飼い主自身の高齢化や健康状態の悪化により、適切なケアが提供できなくなることもあります。特に散歩や日常的なケアが困難になった場合、犬のQOL(生活の質)を考慮して新しい飼い主を探すケースもあるのです。
高齢の飼い主が犬を飼う場合、「万が一のときのプラン」をあらかじめ検討しておくことで、突然の状況変化にも対応しやすくなります。家族や親族との事前の話し合いが重要です。
犬を手放す前に検討すべき対処法

犬を手放す決断をする前に、以下のような代替策を検討してみましょう。状況によっては問題解決の糸口が見つかるかもしれません。
一時的な預かり先を探す
状況が一時的なものであれば、短期間だけ犬を預かってもらえる場所を探すことも選択肢の一つです。友人や家族に一時的に預けることができないか相談してみましょう。
また、ペットホテルや一時預かりサービスを利用することも可能です。費用は施設によって異なりますが、1日3,000円〜10,000円程度が相場となっています。数か月単位の長期預かりに対応している施設もあるので、まずは問い合わせてみることをお勧めします。
問題解決のための専門家相談
犬の問題行動や適応の難しさが理由の場合は、動物行動学の専門家やドッグトレーナーに相談することで解決できるケースもあります。専門家のアドバイスを受けることで、飼い主自身も適切な対応方法を学ぶことができます。
トレーニングの費用は、個人セッションで1回5,000円〜15,000円程度、グループレッスンならもう少し安価な場合もあります。問題の深刻さや複雑さによっては、複数回のセッションが必要になることもあるでしょう。
経済的支援やサポートの活用
経済的な理由で飼育が困難な場合、各地域の動物愛護団体やNPOが提供する支援プログラムを利用できることもあります。フードバンクや低コスト医療サービスなど、様々な支援があるので調べてみてください。
また、獣医師会が運営する低価格の診療サービスや、自治体が提供するペット支援制度もあります。地域によって利用できるサービスは異なるため、まずは地元の動物愛護センターに相談してみることをお勧めします。
環境改善の工夫
住環境の問題が理由の場合、犬が快適に過ごせるよう環境を改善する工夫も検討してみましょう。例えば、防音対策、専用スペースの確保、散歩ルートの見直しなどができないか考えてみてください。
アレルギーの問題であれば、空気清浄機の設置や、こまめな掃除・換気、犬との接触を制限するゾーニングなどの対策を試みることも一案です。これらの対策で十分な効果が得られるかは、アレルギーの重症度や個人差によって異なります。
どうしても手放さなければならない場合の選択肢

あらゆる対策を試みても犬を手放す以外に選択肢がない場合、犬にとって最善の新しい環境を見つけることが重要です。以下に、いくつかの選択肢をご紹介していきます。
信頼できる知人や家族への譲渡
理想的な選択肢は、信頼できる知人や家族に犬を引き取ってもらうことです。こうすれば、犬の様子を時々確認することもできますし、犬にとっても比較的ストレスの少ない環境移行が期待できます。
譲渡の際には、犬の習性や健康状態、好みなどの情報を詳しく伝えておくことが大切です。また、フードや必要な用品も一緒に渡すと、新しい飼い主の負担が軽減されるでしょう。
里親募集サイトやSNSの活用
知人に引き取り手がいない場合は、里親募集サイトやSNSを活用して新しい飼い主を探すことも一つの方法です。信頼性の高い里親募集サイトを選び、応募者との面談を行うなど、慎重に進めることが重要です。
ただし、この方法では犬の性格や特性に合った飼い主を見つけるのに時間がかかることもあります。焦らず、犬にとって最適な環境を提供できる飼い主を見極めることが大切でしょう。
保護団体やシェルターへの相談
地域の動物保護団体やシェルターに相談することも選択肢の一つです。多くの団体では、新しい飼い主を見つけるサポートをしてくれます。特に純血種の犬の場合は、その犬種専門のレスキュー団体が存在することもあります。
ただし、保護団体やシェルターは常に満員状態にあることが多いため、すぐに受け入れてもらえない場合もあることを理解しておきましょう。また、寄付金を求められることもあるでしょう。
最後の選択肢としての安楽死
健康上の深刻な問題を抱えており、苦痛が大きい場合に限り、獣医師と相談の上で安楽死を検討することもあります。これは非常に難しい決断ですが、犬の生活の質が著しく低下している場合には、最後の思いやりの選択肢となることもあるのです。
この決断は、犬の状態を最もよく理解している主治医の獣医師としっかり相談した上で行うべきです。また、家族全員の理解と合意を得ることも重要でしょう。
犬を手放す際の心の準備と対処法
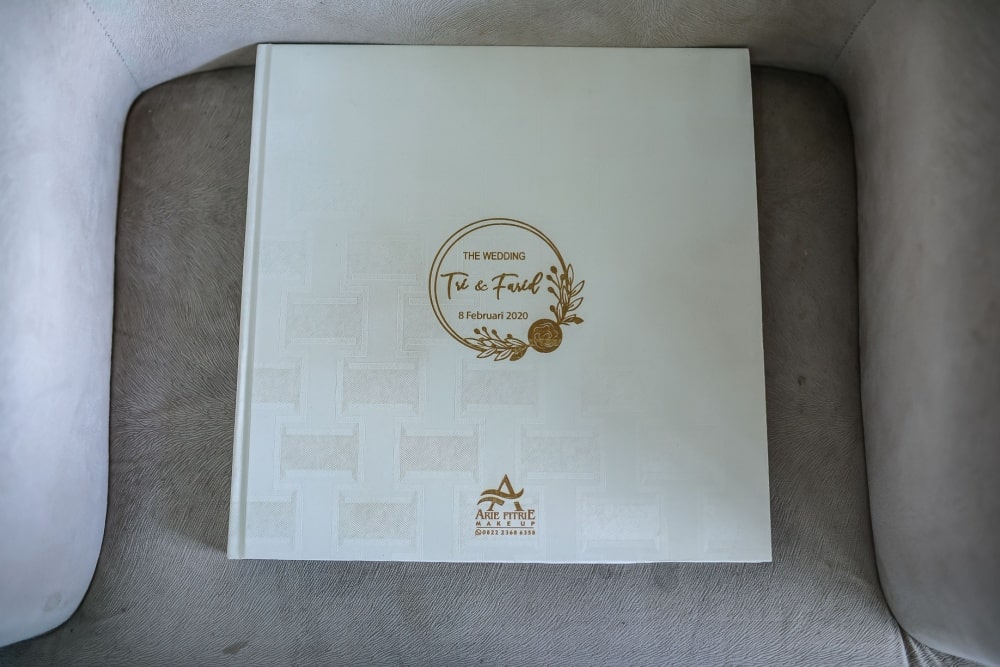
犬との別れは、感情的に非常に辛い経験です。しかし、以下のような心の準備と対処法を知っておくことで、少しでも心が楽になるかもしれません。
罪悪感との向き合い方
犬を手放す決断をした際、多くの飼い主は強い罪悪感を抱きます。しかし、あなたが最善を尽くして考え抜いた末の決断であれば、自分を責め続けることは避けるべきです。
心理学の観点からも、過度な自己批判は心の健康に悪影響を及ぼします。「できる限りのことをした」という事実に目を向け、自分自身を許すことも大切なのです。
お別れの儀式を行う
犬との思い出の品(写真、首輪など)を整理したり、最後の特別な時間を過ごしたりする「お別れの儀式」を行うことで、感情の整理がつきやすくなることがあります。
具体的には、犬との思い出アルバムを作ったり、お気に入りの場所で最後の散歩をしたり、特別なご飯を用意したりすることが考えられます。これらの行為は、区切りをつける助けになり、心の整理を促します。
周囲のサポートを得る
家族や友人、同じような経験をした人々との対話を通じて、感情を共有することも重要です。ペットロスの自助グループやオンラインコミュニティなどを活用してみることもお勧めします。
また、必要に応じて心理カウンセラーなどの専門家のサポートを求めることも検討してください。特に、犬を手放した後に抑うつ感や強い喪失感が長く続く場合は、専門家に相談することが望ましいでしょう。
新しい飼い主とのコミュニケーション
可能であれば、新しい飼い主と連絡を取り、犬の様子を知ることができると安心感が得られます。ただし、あまりに頻繁な連絡は新しい飼い主の負担になる可能性もあるため、バランスを考えることが大切です。
最初のうちは、写真や簡単な近況報告をいただけるよう依頼してみるのも良いでしょう。犬が新しい環境に適応している様子を知ることで、あなた自身の心の整理もつきやすくなるはずです。
犬にとってストレスの少ない別れ方

犬を手放す際は、犬自身のストレスをできるだけ軽減することも大切です。以下のポイントに注意して、犬にとって優しい別れ方を心がけましょう。
環境移行のためのステップ
新しい飼い主が決まった場合、いきなり環境を変えるのではなく、段階的に慣らしていくことが理想的です。例えば、最初は短時間の訪問から始め、徐々に滞在時間を延ばしていくなどの工夫ができます。
また、新しい飼い主に対して、犬の好きなおやつや遊び方を教えておくと、信頼関係構築がスムーズになります。犬の性格や特性、健康状態などの情報も詳しく伝えておくことが大切です。
犬のストレスサインに注意
環境の変化に伴い、犬は様々なストレスサインを示すことがあります。食欲不振、過度の吠え、引きこもり、トイレの失敗などが見られた場合は、ストレスが高まっているサインかもしれません。
これらの兆候が見られたら、新しい飼い主と協力して、犬がリラックスできる環境づくりを心がけましょう。安心できる場所(ケージやベッド)を確保したり、日課を一定に保ったりすることが有効です。
必要な物品や情報の引き継ぎ
愛用していたベッドやおもちゃ、普段使用しているフードなどを新しい飼い主に渡すことで、犬は少しでも安心感を得ることができます。特に匂いのついたブランケットなどは、犬にとって重要な「安心材料」となります。
また、かかりつけの動物病院の情報、ワクチン接種歴、既往症や現在の治療情報なども、しっかりと引き継ぐことが大切です。これにより、新しい環境でも適切なケアが継続されるでしょう。
まとめ:犬を手放す決断と心の整理のために

愛犬を手放す決断は、飼い主にとって人生で最も辛い経験の一つかもしれません。深い絆で結ばれた家族との別れは、強い喪失感や罪悪感をもたらすものです。
しかし、やむを得ない事情で犬との別れを選ぶ場合でも、できる限りの代替策を検討し、犬にとって最善の選択を心がけることが大切です。一時的な預かりや専門家への相談、環境改善の工夫など、様々な選択肢を探ってみてください。
そして、どうしても手放さなければならない場合は、信頼できる新しい飼い主を慎重に選び、犬のストレスをできるだけ軽減する別れ方を心がけましょう。また、あなた自身の心のケアも忘れないでください。
最後に、この辛い経験を乗り越えた先には、新たな日常が待っています。犬との思い出を大切にしながらも、自分自身を責め続けることなく、前に進む勇気を持ってください!




